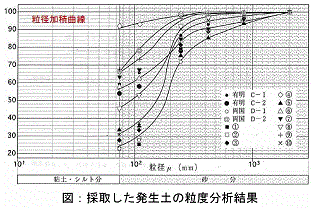リサイクルと技術力
流動化処理工法は、建設現場から発生するどの種類の土(礫・砂・砂質土・粘性土)も適切な製造方法と用途に応じた配合設計を採用することでリサイクルすることができる。
しかし、現場から発生する土は砂分や粘土分の割合が必ずしも一様であるとは限らず、むしろバラツク傾向にある。 理由は、主に現場の掘削作業が深さ方向に行われることにある。 一般に土層は水平方向に一様に堆積する傾向にあるが、深さ方向には砂分と粘土分は分散して堆積する傾向にある。 このため搬出される土は、砂分と粘土分の割合が潜在的に不安定な状態にある。
以下の写真と図に、ストックヤードに集積した土の粒度調査結果を示す(「流動化処理土利用技術マニュアル」写真-1.4及び図-1.3)。 砂分と粘土分の割合は、ある土は90%も粘土分が含まれているのに対して、ある土は20%以下で、全体的に広い範囲に分散することが分かる。
一方、流動化処理土は埋戻しの土工材料として使われるので、一定の品質を確保する必要がある。 このため発生土を原料土とする流動化処理工法には、品質の安定化のために土の搬入から運搬打設の間に色々な技術やノウハウや経験が蓄積されている。 発生土の再生資源化には技術力が不可欠になる。
このため会員は「発生土の選別受け入れ」「砂分と粘土分の分級」「粘性土による泥水の製造と砂質土系の土との適正ブレンド」「製造した泥土や流動化処理土の粘性(フロー値)管理」「砂分含有量の管理」「泥土の状態に応じた配合修正」などの技術を土の状態に応じて、適宜、選択し品質の安定化に努めている。
流動性
流動化処理土は『流動性』をもつので締固めが不要となる。 狭い空間や形状の複雑な箇所でも容易に埋戻し充填が可能で、また、締固め施工が難しい水中の施工もできる。ポンプによる圧送・打設が可能なので施工の大幅な省力化を図ることができる。
流動化処理土の『流動性』は、概ね3段階に分けることができる。
第一段階は、フロー値で概ね110mm(写真1)~160mmのあいだで、この範囲では打設した流動化処理土は自重で降伏し扁平に広く周りに広がる、いわゆるセルフレベリング状態にはならない。 フロー試験の結果を観察しても扁平にはならず山形を呈する。
写真2及び3は、旧建設省土木研究所で実施した実験で、5条6段に組んだ多条埋設管にフロー値110mmの流動化処理土をホッパーで打設した様子を示す。 フロー値110mmは、写真1に見るように必ずしも扁平性は呈していないが、実験では5mm間隔の埋設管の間に流動化処理土がくまなく流れ込み確実な充填が確認された(写真3)。 これは、先に打設された流動化処理土が後から打設された流動化処理土の荷重で押し流されて、セルフレベリングの流動性でなくても狭隘な間隙が充填された、と考えられる。
第一段階の流動性は、発生土の利用率を向上させるために土を多く水を少なくした配合設計だが、低い流動性でも施工の工夫次第で埋戻し充填の性能を確保することができる。
.jpg)
第二段階は、フロー値160mm(写真4)~250mmの範囲で、現場で打設された流動化処理土は1~2%の勾配を伴い流れ広がる。 写真5は、廃坑の埋戻しの様子で、埋戻しの範囲を仮設の仕切り壁で囲うことができないようなときは、配合により勾配を調整することで不要な拡散を抑制できる。 路面下の空洞充填や水中打設(水中での勾配は気中より高い値になる)など流動化処理土の広がりをコントロールするようなときに役立つ。
.jpg)
第三段階は、フロー値250mm~400mmの範囲で、例えば写真6のようにフロー値300mmの流動化処理土を打設すると広い範囲にほぼレベリング状態で流れ広がる(写真7)。 すると打設位置の移動が少なくなるので施工が容易になる利点がある。 なお、流動性の上限は、ブリージング率の設定値から決まり、ブリージング率1%程度を上限とするのであれば、フロー値は400mm程度が限界になる。
.jpg)
このように流動性を調整することで様々な用途の埋戻し・充填・裏込めに使うことができることが特徴としてあげられる。
強度と密度
流動化処理土の『強度』は一軸圧縮強さで評価する。 一軸圧縮強さは、固化材や泥土の密度を調整することにより、用途に応じて100~20,000kN/m2程度まで設定することができる。 流動化処理土の強度の特徴を以下に示す配合設計基準図を使い説明する。
図から同じ固化材量であれば一軸圧縮強さと泥土密度は比例する。一方、同じ強度に対して固化材量と泥土密度は反比例する。 例えば、一軸圧縮強さ300kN/m2に対して、泥土密度1.5t/m3のときC=100kgの組合せになるが、1.55t/m3とき80kg、1.60t/m3のときC=60kgのように、密度の増加につれて徐々に固化材が少なくなる。
この結果から、強度と水セメント比には一元的な関係がないことが推察される。また、泥土密度の変動が大きくなると同量の固化材では、目標とする一軸圧縮強さと差が生まれることが推察できる。
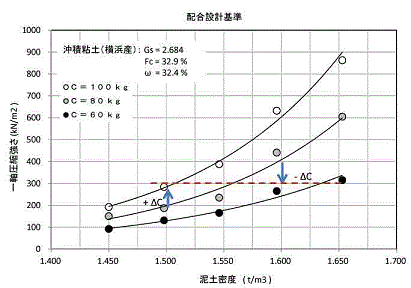
『強度』のもう一つの特徴は、泥土に含まれる砂分(粗粒分)の役割にある。
砂の強度への係わりについて実験をした。 まず、土に含まれる細粒分を分級して、水を加えて細粒分泥土を製造する。 次に、細粒分泥土に固化材を加えて流動化処理土を製造して一軸圧縮強さを求める。 続いて、同じ細粒分泥土(密度一定)に同量の固化材を加えたものに、砂を徐々に加えて密度が異なる流動化処理土を製造し、一軸圧縮強さを求める。 実験で製造した泥土密度に対して一軸圧縮強さをプロットしたものを図2に示す。 図中には、上で述べた方法で実験した4種類の配合(E~H)の試験結果がプロットされている(細粒分の密度と固化材量が異なる)。
図の配合Eに着目すると一軸圧縮強さは、砂を加えて泥土密度が増えたにもかかわらず、同じ強度を示す。 他の配合F~Hからも同様な傾向が読み取れる。 つまり流動化処理土中の砂分の増減は、一軸圧縮強さへの影響が少ない傾向が推察される。 この傾向が流動化処理土の『強度』のもうひとつの特徴になる。
このため原料土の粘土分と砂の割合が安定していると一軸圧縮強さは安定するが、粒度がバラツクと細粒分の絶対量が変わるので、一軸圧縮強さはバラツキはじめる。
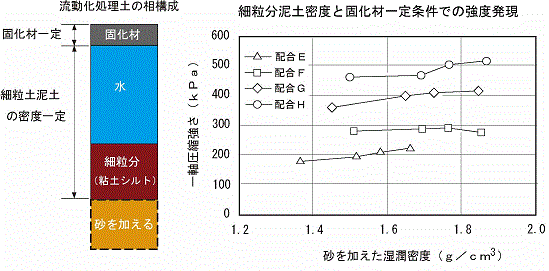
次に、流動化処理土は『強度』と『密度』を一体の品質として考えることにも特徴がある。
流動化処理土の『強度(一軸圧縮強さ)』は荷重で変形が進み土粒子と土粒子を接合するセメンテーション(固結)が破壊されるときの強さに関係する。 一方、『密度』はセメンテーションが破壊されたあとに現われる砂の土粒子間の接触摩擦による抵抗力に関係する。 密度が相当程度高ければ流動化処理土は、セメンテーションの破壊後に、引き続き荷重に抵抗するので大きな変形を抑制する働きがある。
『密度』の効果は、支持力や地盤反力係数とも関連し、密度が高いほど性能が高い。 通常、流動化処理土に荷重が加わると初めにパンチング破壊の現象が現われる(写真1)。 砂分が多く『密度』が1.6t/m3より高くなると、徐々に砂による接触摩擦の効果が表れる実験結果が得られている。
また、『密度』は流動化処理土の体積に占める割合(間隙)に関連し、『密度』が高いほど土粒子の割合が多くなり間隙が小さくなる。 すると流動化処理土の透水性が小さくなり(写真2)耐久性が向上し、水による浸食を抑制する効果が大きくなる。
.jpg)
材料分離抵抗性
流動化処理土の材料分離抵抗性は、打設後に水が表面に浮上がるブリージング水の浮上がりと、付随して発生する砂礫の沈降に関連する。 ブリージング水が大量に浮上がるとセメント分が水と共に溶出し、表面近くの強度が低下することがある。 その結果、乾燥後に表面に亀甲状のひび割れが発生することがある。 このようなときは、同時に流動化処理土中の砂礫が下方に沈降しているので、下部の密度が大きくなり、強度が増加する。 このため全体として均等な強度分布が失われるようになる(図1)。
材料分離抵抗性は、ブリージング水の量を測定することで判断する。 材料分離抵抗性は、泥土及び流動化処理土の粘性に関係し、粘性が不足するとブリージングと沈降がおこる。 粘性を向上させには含水量を減らすか、細粒分を多くする。
ブリージング率1%程度までであれば(写真1及び2)、砂礫の沈降が抑制される粘性状態にあることが実験により確認されている。
.jpg)
ブリージング率1%程度の流動化処理土でも表面にひび割れが発生することがある(写真3)。 これは、表面が気中に露出し表面の乾燥が進む冬場に発生することが多い。
ブリージング水の発生が少なければ、ひび割れは表面の乾燥によるひび割れと判断できる。
コンクリートのように養生すると、この表面に現れる乾燥ひび割れは抑制できる。例えば、覆工板があると表面の乾燥が緩和されるのでひび割れの発生は抑制される(写真4)。 ただし、流動化処理土の表面を養生することは、せん断応力が加わるような場所でないなら、通常、おこなわない。
なお、ブリージング率1%以下の流動化処理土の表面にひび割れが発生しても、表面の固化強度が所要の値であれば、そして埋戻しの用途が圧縮荷重の条件下であれば、性能上の問題はないと工学的に判断される。
.jpg)
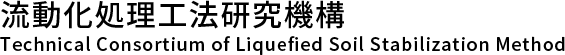
.jpg)