動画によるご説明
流動化処理工法の全体像を把握して頂くために動画を用意しました。 ここでは現場にプラントを設置して流動化処理土を製造する施工を紹介します。 常設のプラントで流動化処理土を製造する場合もほぼ同じ施工になります。
流動化処理土は発生土を原料土として使いますが、この動画では3タイプある製造工程の内、1)低品質の発生土(粘性土)に水を加え解泥し粘度調整用の泥水を製造し、2)次に砂質系の発生土を加え、3)最後に固化材を添加して混練りする、ケースを紹介します。
音声による説明を動画と合わせてお聞きください。
ご挨拶(工法開発の経緯について)
真に信頼できる埋戻し・裏込め工法を目指して
昭和50年代半ば頃だったでしょうか。それまではあまり気になりませんでしたが、構造物基礎や地中構造物、及び都市の各種ライフライン等の埋戻しや裏込めに際して、施工後、時を経て当該路面に陥没や、不測の不陸が生じはじめたことによる障害、事故が多発し始めました。
その以前は、このような地下構造物の埋戻し工事の際に採用されていた埋戻し工法には、良質な砂、砂利を主体とした「川砂」で水締め打設する方法が主に用いられてきていましたが、その頃から「川砂」の採取が制限されるようになって、代わりに、「山砂」が使われるようになりました。
しかし、同じ「砂」と言っても、「山砂」はかなりの量のシルト、粘土の細粒分も含んだ、いわば「砂質土」と称すべきもので、決して「砂」に代わる材料ではなかったのです。
従って、「砂質土」を用いて地山との間に残された狭隘な掘削空間を埋戻し、十分な締固めがしにくいままに供用した場合には、埋戻し部の緩い砂質土は地下漏水によって侵食され始め、結果として地中に思わぬ空洞を発達させてしまったために、路面の不陸、ひいては路面陥没につながる災害の原因になっていたと判断されますし、確かに下水管内に多量の流出砂質土の堆積が確認されました。
この実情を憂い、それに誘引されたと思われる不測の地中空洞の補填を含めて、締固め不要な、いわば「土のコンクリート工」とも見なせる「土の流動化処理工法」の開発を試みました。勿論、それ以前に開発された、より高品質な埋戻し材や、水中盛土技術をも参考にして、より入手し易い土質材料を活用し、用途別に、技術的にも、経済的にも、より広範な要求に対応が可能な当工法の開発を続けてきました。そして平成になって、先の建設省総合技術開発プロジェクト「建設副産物の発生抑制・再生利用技術の開発」の一環として、当時の建設省土木研究所と日本建設業経営協会中央技術研究所が行った、流動化処理土の利用技術に関する4年間の共同研究により、流動化処理工法の効用と、その実用性の第一段階の確認を得ることができました。
本機構の設立前、及び設立後の我々の流動化処理土の施工実績の推移を図示しました。平成10年、11年にかけて東西都市圏において大規模な地下鉄関連工事が集中したこともあって、その間の実績は急激に増加し、それに応ずることで技術をさらに習熟し得たことは幸せでした。そしてこの間、当工法に協賛された会員の分布が都市域に限られず、全国規模に広がり始めたことは大変心強く思います。
この段階で、本機構に対する建設業界の広いご理解により、「流動化処理工法」は一応の市民権を得たものと感じております。しかし、その有用性が認められ、施工対象も、施工量も増えるにつれて、個別に当工法、並びに処理土に関する技術的研究、普及に励むことが許されぬ時流を感じ、流動化処理工法に関連する特許権等の監理、並びに技術指導、広報活動を主務とする組織が併存されるべきとの判断から、別組織として新たに「(有)流動化処理工法総合監理」を平成13年末に発足しました。
当組織は本機構と密接な連携関係にあることが必要なため、流動化処理工法研究機構の特別会員として迎え、今後は、より実務的に流動化処理工法の発展を支える基盤となるものと信じております。
なお、この結果、独立行政法人土木研究所、有限会社流動化処理工法総合監理、及び社団法人日本建設業経営協会の三者間には、平成14年10月1日付で「流動化処理工法パテント・プール契約」が締結されていることを追記いたします。

流動化処理工法の生い立ち
「流動化処理工法」と聞かれると、多くの方が当今、問題になっている建設副産物である、建設発生土、泥土の有効な再利用のための工法として開発された、新しい工法と理解しておられるようです。それも間違いとは言い切れませんが、実はこの工法の生い立ちは、未だ建設副産物の処理が問題になる以前の、昭和60年以前に遡る経緯があるのです。 現在、この工法はかなり広く建設業界に受け入れられるようになりましたので、「流動化処理土、流動化処理工法」の命名者と、自ら任じている本機構の名誉理事長の久野悟郎の懐旧談の形をかりて、この工法の出生の過程をご説明したいと思います。
今後、ご利用頂く上に、お役に立つと信じますので、少し長くなりますが、ご興味があれば是非お読み下さるようお願いいたします。
「流動化処理土」とはどんなもの?
いわば「土のコンクリート」と言うべき「流動化処理土」が、いわゆる「土」 や本物の「コンクリート」と比べて、どんな性能の材料か、どんな泥でも本当に固まることが出来るのか、締固めでは密度を高くすることが必須であるが、流動化処理でも密度の高い処理土を実際に作ることができるのか、そして、それが本当に必要なのか、また、流動化処理土に欠点があるとすれば、それを補う方策があるか、など、色々の疑問を持たれるのはもっともなことです。
流動化処理土が世に出て、まだ二十年にはなりません。コンクリートが百五十年を越える歴史を持つのと比べれば、まだ、分からないことが山積しているのも当然かも知れませんが、ここに、今までに分かっている目新しい性能を説明します。
そして、今後、流動化処理土はどうあるべきか、考えを述べさせてもらいます。
配合設計・品質管理のためにどのような試験を行うか?
まず、使用目的に合致するような流動化処理土を得るために、流動化処理土を構成する主要な三要素である、
「調整泥水」、「建設発生土」、及び「固化材」をどのように配合したらよいか、決めることが必要です。更に必要に応じて添加剤、補強材を配合することもあり得ます。この作業を「配合設計」と呼び、重要な試験であることは言うまでもありません。
また、決まった配合通りの製品が間違いなくプラントで製造されているか、現場に打設されているかを確認するための「品質管理」も、勿論、大切です。 詳細については、次の各項目をご参照下さい。
流動化処理土をどのように製造するか?
流動化処理土を製造するには、一般的に「調整泥水」、「建設発生土」、「固化材」が必要です。更に添加剤、あるいは補強材が必要なこともあります。、これらを決められた配合通りに、均質に混合しなければなりません。
そして、「調整泥水」、「建設発生土」の供給体制や、使用される工種、現場の状況に応じて、もっとも能率的な製造工程を選ぶことが必要なことは言うまでもありません。流動化処理土の製造の工程を模式的に説明すると次の通りです
なお、混和剤、あるいは補強材等を混合する必要のある場合は、
その作業に必要な設備を追加する必要があります。
流動化処理土の利用される現場は、コンクリートの場合と比べると、比較の対象にはならないくらい多様です。処理土自体の性能からしても捨てコンクリートに近い高級なものから、並みの沖積地盤対応の均質な埋戻しでよい場合まで、非常に広い範囲に渉ります。従って、品質管理の厳密さも担当者の技術的判断に待つ面が多いと思います。例えば構成土質の変化を色調の変化で察知し、その際には集中的に管理試験の頻度を増すといった柔軟な配慮が求められるべきだと考えます。
また、品質管理とは言えないかも知れませんが、流動化処理土を打設して、つぎの作業上、打設面に作業員が載れるかを判定すべく、その固化の進行度を知りたくなります。簡易な判定法の一つとして土壌の硬度を測定できる、一種の簡易貫入抵抗測定器である、「山中式土壌硬度計」が活用された実施例があります。
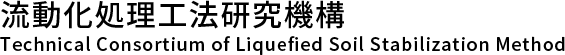










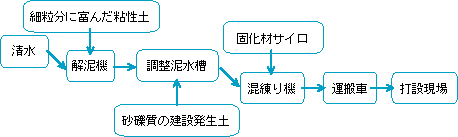
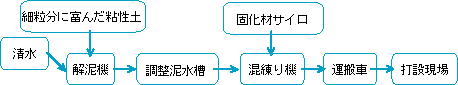
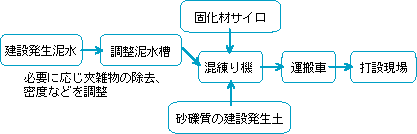
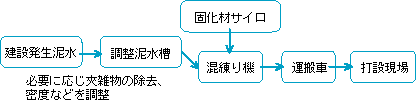
盛土などの土構造物の築造には締固めが不可欠であるが、
それを妨げる特殊事情が日本では多すぎる